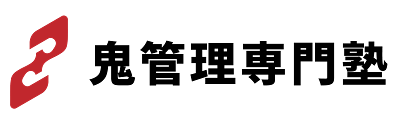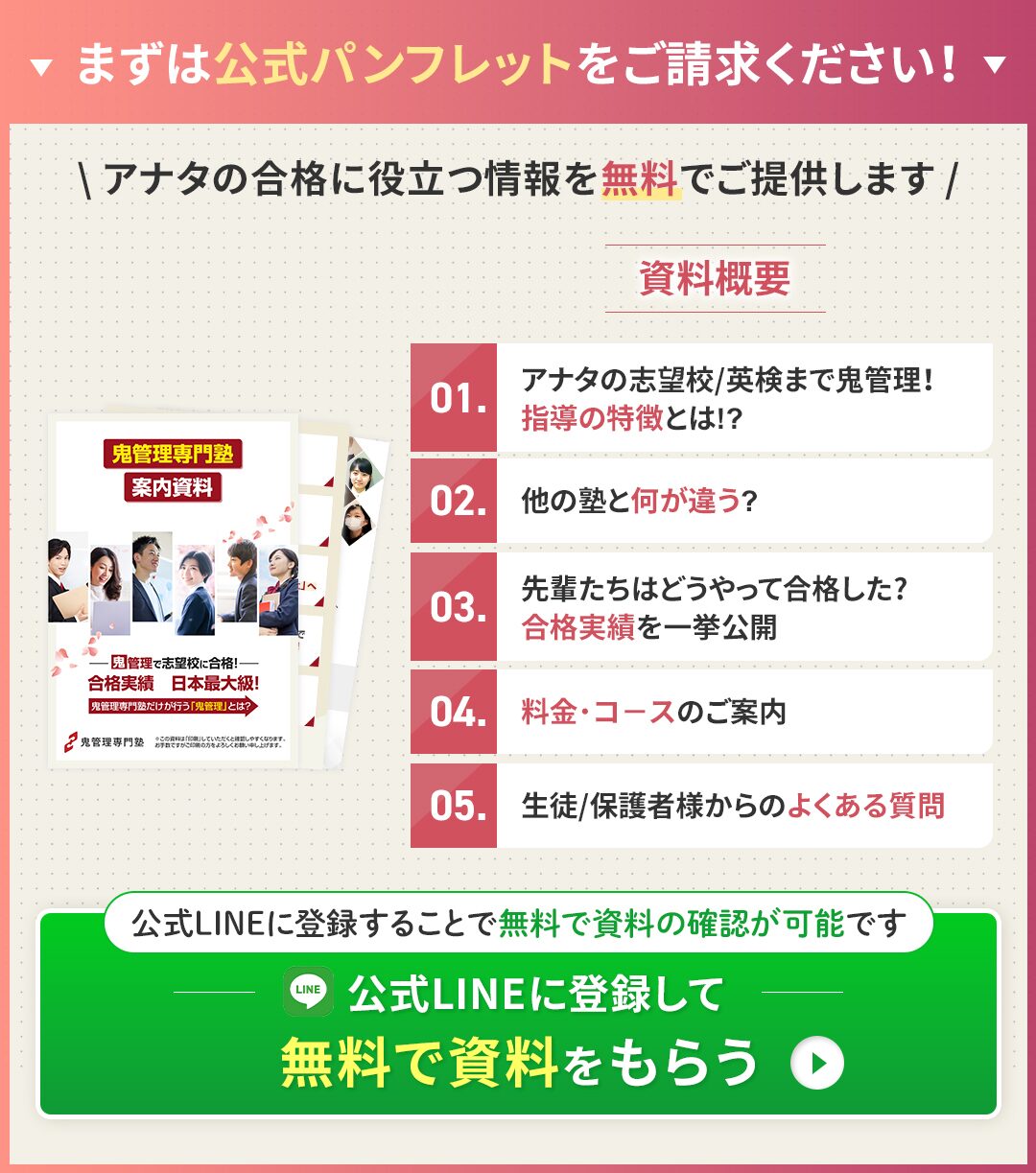大学受験の勉強法は?
志望校ごとに勉強法を変えるべき?
得意分野と苦手分野どちらを優先すべき?
この記事にたどり着いたあなたは、大学受験のための勉強法がわからず不安に思っているのではないでしょうか。
結論、志望校合格のためには自分に合った勉強法を確立するのが重要です。
自分の志望校に合わせた学習計画を立て、継続的に勉強を進められた人が合格を勝ち取ります。
本記事では大学受験のプロが差をつける戦略的な勉強法や、主要科目の具体的な勉強方法など、大学受験の勉強法を徹底解説します。
「受験までに何をすればいいか分からない」「勉強方法が確立できていない」という方は、ぜひ最後まで読んで志望校合格への参考にしてください。
先に主要科目別の勉強法を知りたい方は「【科目別】大学受験の主要科目3つを勉強するコツ」を参考にしてみましょう。
なお、大学受験のプロからサポートを受けたいときは、受験生の徹底的な勉強管理を支援してくれる「鬼管理専門塾」の利用もご検討ください。
効果的な勉強法は下記のとおりです。
- 志望校に合わせた学習計画を立てる
- 苦手科目を優先して勉強する
- 主要教科の基礎固めをする
- 隙間時間を活用する
- モチベーション維持に努める
- 生活習慣を整える
大学受験のプロが教える効果的な勉強法を実践して、志望校合格を目指しましょう。
詳しくは「大学受験で差をつける6つの戦略的な勉強法」を読んでみてください。
大学受験のために優先して勉強しておく主要科目は「英語」「国語」「数学」です。
受験する学部や専攻分野にもよりますが「英語」「国語」「数学」は、多くの大学で受験科目に入っており、特に「英語」は配点が高い傾向にあります。
各科目の勉強方法については「【科目別】大学受験の主要科目3つを勉強するコツ」を参考にしてみてください。
大学受験で差をつける6つの戦略的な勉強法
大学受験で差をつける6つの戦略的な勉強法は以下のとおりです。
実践することで確実に合格に近づけるものばかりなので、すぐに実践してみてください。
志望校に合わせた学習計画を立てる
大学受験の成功には、志望校に合わせた学習計画を立てることが欠かせません。
大学や学部ごとに求められる知識が異なるため、自分の目指す大学や学部に合わせた計画を立てることが重要です。
たとえば、難関大学を志望する場合は、基礎から応用まで幅広い範囲で深い理解が求められます。
また、高校入試と大学入試では同じ偏差値でもレベルが違う点にも注意しましょう。
成績上位者が難関大学を受験する傾向にあるため、在籍している高校の偏差値と志望大学の偏差値が同じ50でも、志望大学に合格するには偏差値60程度の学力が求められます。
しかし、実際に自分で学習計画を立てるのは簡単ではありません。
志望校合格から逆算し、どの科目をどれだけ勉強すればいいのか、どのタイミングでどの教材を使うべきかなど、考えるべきことは多岐にわたります。
そこで、塾や個別指導などのサービスを利用するのが一つの有効な手段です。
専門の講師が受験生一人ひとりの状況に合わせたカリキュラムを作成し、計画的な学習をサポートしてくれます。
たとえば、大学受験生におすすめの「鬼管理専門塾」では、生徒一人ひとりに合わせたカリキュラムの作成を実施。
合格から逆算し目標を立て、常に何をすれば良いかを明確にするうえ、受験生が徹底的な学習計画の管理を行えるように、効率的な学習をサポートしてくれます。
苦手科目を優先して勉強する
志望校の合格を目指すには、得意科目を伸ばすよりも、苦手科目を克服するのが重要です。
得意科目で高得点をとれても、苦手科目の点数が低いと全体の成績が下がり、合格は難しくなるでしょう。
たとえば理系生徒の場合、数学や物理が得意であっても、英語や国語の受験勉強に苦戦することがあります。
苦手科目を重点的に勉強し、最低限の得点ラインを超えることができれば、全体の成績は大きく向上します。
苦手科目の克服には、まず「何につまずいているのか」原因をはっきりさせるのが重要です。
解決策を行動レベルまで落とし込めれば、基礎を理解できて苦手科目の克服につながります。
勉強の効率が上がり、限られた時間の中でより多くの内容を定着させられるでしょう。
主要教科の基礎固めをする
受験勉強において、主要教科の基礎固めは非常に重要です。
基礎がしっかり身についていない段階で応用問題や過去問に挑戦しても、効果的な学習にはなりません。
むしろ、理解が不十分なまま応用問題に挑むと、理解が進まずに勉強時間を無駄にする可能性があります。
特に大学入試で重要な科目の「英語」「国語」「数学」はしっかりと基礎を固めましょう。
たとえば、英語では単語や文法の意味を徹底的に覚えるのが重要です。
また、国語でも単語や文法、漢字などの意味合いを理解しておく必要があります。
数学においては、基礎問題の理解を徹底しましょう。
基礎固めの段階で自信をつけ、その上で徐々に難易度の高い問題に挑戦していくのが、モチベーションを維持しつつ効果的に学習を進めるポイントです。
先に主要科目の勉強法を知りたい方は「【科目別】大学受験の主要科目3つを勉強するコツ」を参考にしてみてください。
隙間時間を活用する
受験勉強で成功するには、限られた時間を最大限に活用するのが大前提です。
隙間時間とは、通学の電車やバスの中、部活の休憩時間や家事の合間など、日常生活の中にある短い時間を指します。
隙間時間を勉強にあてることで、まとまった勉強時間が取りにくい人でも、学習時間を増やせるでしょう。
隙間時間を活用するには、移動中や外出中でも「どうにかして1分1秒でも勉強時間を作れないか?」という姿勢が重要です。
たとえば、スマートフォンやタブレットを使い、電子書籍の参考書や問題集を読むのも良いでしょう。
英語のリスニング教材であれば移動中に音声で学習ができます。
隙間時間を最大限に活用することが、志望校合格への近道です。
モチベーション維持に努める
受験勉強は長期間にわたる戦いのため、途中で挫折しないためにモチベーションの維持に努めましょう。
「受験に合格するためのモチベーション」は以下の2つです。
- 絶対に合格したいという強い思い
- 勉強そのものが楽しくてやめられないようにする
「なぜ難関大学に合格しなければならないか」を理解することで、絶対に志望校に合格したいというモチベーションを維持しやすくなります。
勉強そのものを楽しくするには、昨日の自分と今日の自分を比較して「単語を10個覚えられた」など、良い部分を評価してあげましょう。
少しずつ勉強を覚えられる範囲が増えると「自分はやればできる」という思いにつながり、気分を高めやすくなるはずです。
また、勉強を続けるうえでは、仲間との切磋琢磨もモチベーション維持に有効です。
同じ目標を持つ仲間と一緒に勉強することで、お互いに励まし合い、競い合うことができます。

鬼管理専門塾には、Zoom自習室があります。
全国の仲間と一緒に自習ができるので、ひとりでは勉強の集中力が続かない方も、モチベーションを維持しやすいでしょう。
生活習慣を整える
効率的に勉強を進めるには、生活習慣を整えましょう。
特に、朝型の生活に切り替えるのが重要です。
朝型の生活に切り替えることで、集中力が高まる時間帯に勉強を進められ、より効率的に知識を吸収できます。
また、入試は朝に行われることが多いため、朝に最大限のパフォーマンスを発揮できる状態にしておくのが良いでしょう。
一方、夜型の生活は勉強に適していません。
夜遅くまで勉強すると、睡眠時間が短くなり、翌日の集中力や体調に悪影響を及ぼします。
受験生は「睡眠が命」であり、1日に8〜10時間の睡眠を取るのが理想とされています。
十分な睡眠は脳の働きを良くし、記憶の定着を促進させるため、睡眠時間はしっかり確保するようにしましょう。
【科目別】大学受験の主要科目3つを勉強するコツ
大学受験で必須の主要科目3つの効果的な勉強法を解説します。
効果的に受験勉強を進めるには、抽象的な勉強方法を具体化することが重要です。
勉強方法を行動できるレベルまで細分化できると、合格に必要な点数を獲得するための理解が進みます。
ぜひ勉強法を参考にして、日々の勉強に取り込んでみてください。
英語
英語は大学受験において、志望校にかかわらずほぼすべての受験生が取り組む必須科目です。
多くの大学では英語の配点が高く設定されており、難関大学を目指す場合、英語の得点力が合格へのカギとなります。
英語の勉強法は「単語・熟語編」「文法・構文編」「長文読解編」で、下記表にまとめているので参考にしてみてください。
【英語(単語・熟語編)】
| 勉強法のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1.単語を見て、意味が一瞬で理解できるようにする | 単語を見た瞬間にその意味をすぐに理解できるようにすることを目指す ※長文読解が苦手な理由は「単語」と「文法」を覚えていないから |
| 2.イメージで覚えられるようにする | 単語を意味だけでなく、具体的なイメージと関連付けて覚える |
【英語(文法・構文編)】
| 勉強法のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1.見開きの熟読 | 文法や構文の解説を見開きでしっかりと読む ※黙読→音読の流れで理解して読む |
| 2.テーマの結論・概要を文章化 | テーマごとに結論や概要を自分の言葉で文章化する |
| 3.結論・概要を解説できるようになる | 作成した結論や概要を他人に説明できるように練習する |
【英語(長文読解編)】
| 勉強法のポイント |
|---|
| 1.問題を制限時間で解く&解答の根拠もメモ |
| 2.解答を確認し、正解(〇)と不正解(×)のみを記録する ※正しい選択肢までは見ない |
| 3.〇×を元に、再度解答する ※根拠を含めメモする |
| 4.再解答を確認し、根拠が合っているか確認する |
| 5.根拠が間違っていた場合、問題内容が正答できなかった原因を分析し、改善策を検討する |
| 6.問題文を精読して理解を深める |
| 7.問題文を音読して理解を深める |
上記のように、英語の学習は基礎から順序立てて進めるのが重要です。
英単語や文法などの知識を確実に身につけ、それを基にして長文読解に取り組むことで、総合的な英語力が向上します。
日々の積み重ねを大切にし、計画的に学習を進めれば、高得点を狙える英語力を身につけられるでしょう。
国語
国語には「現代文」と「古文」の2つがあり、どちらも大学受験において重要な科目です。
文系の受験生だけでなく、国公立大学を志望する理系の受験生にとっても重要科目のため、効率的に勉強を進める必要があります。
国語の勉強法について、現代文は「単語編」「長文読解編」でまとめています。
古文についても「単語編」「長文読解編」でまとめているので、ぜひ以下表を参考にしてみてください。
【現代文(単語編)】
| 勉強法のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1.KW系の参考書を準備し、理解を深める | KW系(キーワード系)の参考書を用意し、見開きごとに内容をしっかりと理解しながら読む ※漢字などの理解も同じ形で進める |
| 2.単語をノートに書き出す | 単語をノートに書き出し、自分の言葉で説明できるようにする (丸写しや丸暗記は避ける) |
| 3.確認と理解を繰り返す | 次の見開きに進んで、同じ作業を繰り返す。また、前の見開きに戻って再度確認する ※KW系の参考書と単語の学習ができたら、基礎的な参考書を使って現代文の読み方・解き方を練習する |
【現代文(長文読解編)】
| 勉強法のポイント |
|---|
| 1.問題を制限時間で解く&解答の根拠もメモ |
| 2.解答を確認し、正解(〇)と不正解(×)のみを記録する ※まだ正しい答えを書き込まない |
| 3.〇×の結果をもとに、再度問題を解答する ※根拠を含めメモする |
| 4.再解答を確認し、根拠が合っているか確認する |
| 5.根拠が間違っていた場合、問題内容が正答できなかった原因を分析し、改善策を考える |
| 6.問題文を精読して理解を深める |
【古文(単語編)】
| 勉強法のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1.わからない単語とわかる単語に分類する | 分からない単語を覚えるために工夫する(背景理解、語呂合わせなど) ※「古文単語」や「慣用句」を覚えるための参考書を使用する |
| 2.赤シートで隠して繰り返し覚える | わからない単語を何度も繰り返して覚える ※基礎力が不足している場合は、初歩レベルの入門書を併用して学習する (難関大学に受験したい方で、偏差値55以下の場合) |
| 3.瞬時に理解できるまで繰り返す | 分からない単語がなくなるまで繰り返す |
【古文(長文読解編)】
| 勉強法のポイント |
|---|
| 1.問題を制限時間で解く&解答の根拠もメモ |
| 2.解答を確認し、正解(〇)と不正解(×)のみを記録する ※正しい選択肢までは見ない |
| 3.〇×の結果をもとに、再度問題を解答する ※根拠を含めメモする |
| 4.再解答を確認し、根拠が合っているか確認する |
| 5.根拠が間違っていた場合、問題内容が正答できなかった原因を分析し、改善策を考える |
| 6.問題文を精読して理解を深める |
現代文も古文も基本的には、単語・文法などの理解を進めてから、長文読解をマスターする順番で勉強を進めます。
基礎知識を確実に身につけ、読解力を鍛えることで、高得点を狙える力を養いましょう。
数学
数学は理系志望者にとって必須の科目であり、他の受験生と差をつける重要な科目です。
また、文系であっても国公立大学を志望する場合、多くの方にとって数学は避けて通れないでしょう。
効率的に数学を学ぶためには、段階的な学習と体系的な理解が必要です。
数学の勉強法と攻略法のポイントは以下のとおりです。
【数学勉強法】
| 勉強法のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 1.基礎問題を徹底して理解する | 基礎的な問題を徹底的に解き、基本的な知識と解く方法を確実に身につける |
| 2.標準レベルの問題を解く | 基礎が固まったら、標準レベルの問題に取り組み、応用力を養う |
| 3.入試レベルの問題を解く | 標準レベルの問題に慣れてきたら、入試レベルの難しい問題に挑戦し、試験本番に向けた実践力を高める |
| 4.実践と過去問を反復する | 入試に近い形式で実践問題や過去問を繰り返し解き、試験に慣れる |
【数学攻略法】
| ステップ | 詳細 |
|---|---|
| 1. 体験 | 問題を解いて、自分の実力を知る 現在の理解度や解く方法の速さを確認する |
| 2. 整理 | 反省点や間違いを振り返り、改善点を考える どこで間違えたのか、なぜ間違えたのかを分析して次に生かす |
| 3. 再体験 | もう一度、同じ問題を解いてみる 前回の間違いを踏まえて、正しい解法を実践して理解を深める |
| 4. 探求 | 新しい公式や別ルートでの解答方法を模索する 角度の違う問題文でも対応できる能力を身につけるため、多面的な知識や理解を深める |
数学は特に基礎問題を徹底して理解するのが重要です。
上記のステップを実践し、計画的に勉強を進めることで、高得点を狙える力が身につくでしょう。
数学は継続的な努力と体系的な学習が重要なので、日々の学習を大切にし、目標に向かって進んでいきましょう。
大学受験の勉強を始めるときの準備
大学受験の勉強を始めるには、はじめに志望校の決定や現時点での実力を把握して準備をしましょう。
準備を的確に進めることで、志望校合格への道筋が明確になります。
以下のポイントを参考に、受験勉強を始める準備を進めてみてください。
志望大学や学部を決める
志望校や学部を決めることで、大学や学部に合わせた受験勉強を進められます。
具体的な目標を設定すると、学習計画を立てやすくなり、モチベーションの維持にもつながるでしょう。
また、大学や学部ごとに試験内容や出題傾向には特色があります。
志望校が早期に決まれば、特定の試験対策に集中できるはずです。
たとえば、英語の長文読解の配点が高い大学を受験する場合、長文読解の練習に重点を置きます。
また、数学において難易度の高い応用問題が出る傾向がわかっていれば、早期に対策を練れるでしょう。
志望大学を早く決めることで、受験勉強を効率的に進められるだけでなく、試験のクセに慣れるための時間を確保できます。
現時点での自分の実力を把握する
模試を活用して、現時点での自分の実力を把握するのも重要です。
模試の結果を分析することで、自分がどのような教科や問題に強いのか、逆にどの部分が弱点なのかを把握できます。
結果をもとに、学習の優先順位を決められます。
また、志望校の合格ラインや入試の傾向を調べ、それに対して自分の現在の実力との差を明確にするのも効果的です。
たとえば、志望校の合格ラインが偏差値70で、自分の現時点での偏差値が60であれば、どの科目でどれだけの得点アップが必要かを具体的に考えます。
そのために必要な教材や学習方法、勉強時間の配分を決めていきましょう。
現時点の自分の実力を把握できると、志望校合格から逆算して「何をするべきか」が明確になります。
入試の流れ・入試科目を確認しておく
大学入試の流れは複雑であり、国公立大学と私立大学で異なる点も多いため、志望校の入試制度を確認しておくのも重要です。
ここでは、国公立大学と私立大学の一般的な入試の流れと科目を説明します。
| 大学の種類 | 試験概要 | 内容 | 主な科目(例) |
|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 共通テスト | 全国一斉に実施される統一試験 基礎的な学力を評価 | 国語、数学(Ⅰ・A、Ⅱ・B)、英語、理科(物理、化学、生物)、地理歴史、公民 |
| 二次試験 | 各大学が個別に実施する試験 専門的な知識や応用力を評価 | 大学・学部ごとに異なる(例:数学、英語、小論文など) | |
| 私立大学 | 一般入試 | 大学ごとに実施される試験 各大学の個別試験で合否が決まる | 国語、英語、数学、選択科目(理科、社会など) |
国公立大学の入試は、主に「共通テスト」と「二次試験」の2段階で行われます。
また、私立大学の入試は、大学ごとに異なる場合が多く、主に「一般入試」と「推薦入試(AO入試含む)」に分かれます。
志望校の入試制度を正確に把握すると、受験勉強の計画がより明確になります。
たとえば、共通テストで高得点を目指す場合は、全教科の基礎をしっかりと固めるのが重要です。
一方、私立大学の一般入試では、特定の科目に対する理解が求められる場合が多いです。
志望校の入試科目を事前に確認し、ポイントに絞って勉強を進めましょう。
各大学の入試情報は、大学の公式サイトや入試要項で詳細に確認できるため、定期的にチェックするのがおすすめです。
自分なりの学習スタイルを模索する
勉強の効果を最大化するためには、どのような勉強方法が自分にとって効果的であるかを模索し、習慣化することが必要です。
しかし、限られた受験勉強期間の中で、最適な学習スタイルを見つけるのは難しいと感じるかもしれません。
「自分なりの学習スタイルをすぐに身に着けたい」という方には、鬼管理専門塾がおすすめです。
鬼管理専門塾では、受験生が効果的に勉強を進められるよう、さまざまなサポートを提供。
中でも「毎日勉強報告システム」や「問題発見ミーティング」は、勉強の習慣を身につけ、自分なりの学習スタイルを確立するのに役立ちます。
| 毎日勉強報告システム |
|---|
| 毎日勉強報告システムでは、毎日の勉強内容や時間を記録し、課題と解決策の報告をしてもらいます。 毎日の勉強が習慣化され、課題が明確になるなど、勉強を自己管理しやすい体制が整えられるのです。 |
| 問題発見ミーティング |
|---|
| 問題発見ミーティングでは「なぜ間違えたのか?」「どのようにしたら二度と間違えないのか?」を講師と対話することができます。 問題の原因と解決策がわかり、成績を向上させるために必要な気づきを得られます。 |
大学受験の勉強法で失敗しないための注意点
志望校合格のためには、効率良く勉強を進める必要があります。
以下の失敗しないための注意点を知っておくと、より効率を上げられるでしょう。
全教科で同じ得点を目標としない
各教科の得点配分や必要な得点は、志望校や学部によって大きく異なります。
自分が目指す大学や学部の試験内容と配点を把握し、優先的に勉強する教科を選ぶのが重要です。
たとえば、理系学部を志望する場合、数学と理科に多くの時間を割き、高得点を目指すのが効果的です。
一方で文系学部を志望するなら、英語と国語を重点的に勉強し、得点を稼ぐことが重要になります。
実力に見合った参考書・問題集を使用する
自分の実力に見合った参考書や問題集を使用することで、効率的に学習を進めることができます。
具体的には、自分にとって少し簡単に感じるレベルの問題から挑戦するのが効果的です。
基礎が意外と理解できていないケースも多いため、簡単な内容から少し難しい内容の順番で勉強できると、無理なく徐々に実力を向上させられます。
特に苦手な科目については「入門書」レベルの参考書から始めることをおすすめします。
漫画形式の書籍や動画教材を活用することで、難しい内容も分かりやすく学べるでしょう。
たとえば、大学受験生におすすめの「鬼管理専門塾」では、以下のようなステップで学習を進めることをおすすめしています。
| ステップ | 詳細 |
|---|---|
| 1.基礎力要請 | まずは講義系の参考書を使って、基礎的な知識をしっかりと身につけます。 この段階では、自分の実力に合わせた易しい参考書から始めると良いでしょう。 基礎力が高い人は、2番目のステップから始めることも可能です。 |
| 2.発展的学習 | 基礎が固まったら、難易度の高い参考書に挑戦します。 ここでは、応用問題や発展的な内容を含む参考書を使って、さらに深い理解を目指しましょう。 |
| 3.過去問題集 | 最後に、過去問題集を使って実践的な練習を行います。 過去問を解くことで、試験の出題傾向や時間配分に慣れ、本番に備えることができます。 |
過去問題集は最後に取りかかる
過去問題集には最後に取りかかりましょう。
まずは「参考書(講義系・演習系)」を使って、基礎力を身につけるのが重要だからです。
下記を参考に、過去問題集に取り組むタイミングを考えてみてください。
| 基礎力がある人の場合 |
|---|
| 基礎力がしっかりと身についている人は、応用レベルの参考書を使ってさらに発展的な問題に挑戦できます。 この段階で、難易度の高い問題を解き実力を強化し、その後に過去問題集に取り組むことで、実際の試験に近い形式での練習が可能です。 応用力を高めた状態で過去問に挑戦することで、試験本番に向けた実践的な準備が整います。 |
| 基礎力がないと感じる人の場合 |
|---|
| 基礎力が不足していると感じる人は、まずは参考書を徹底的に活用して基礎力を固めるのが重要です。 講義系の参考書を使って基本的な知識を習得し、演習系の問題集を使ってその知識を定着させます。 基礎がしっかりと固まった後で、過去問題集に取り組めば、より効果的に学習を進めることができます。 |
志望校の過去問題集に取り組むのは、試験対策の最後の仕上げとして非常に重要です。
過去3~5年分の過去問を解くことで、志望校の出題傾向や難易度を把握し、試験本番に向けた対策を練ることができます。
また、時間を計って過去問を解いておき、試験の時間配分や本番の雰囲気に慣れておきましょう。
共通テスト対策もしっかり行う
共通テストは全受験生が受ける試験であり、試験結果は国公立大学の一次試験の結果として大きな影響を与えます。
私立大学の入試においても共通テストの成績を利用できる場合があります。
最近の共通テストでは、以前のセンター試験に比べて「応用力」や「思考力」が試される傾向が強いです。
単純な知識の暗記ではなく、実際にその知識をどのように活用するかを問われる問題が多く出題されます。
そのため、知識の理解を深めながら、応用力を鍛える練習を繰り返すことが重要です。
大学受験の勉強を継続するための工夫3つ
大学受験の勉強は長期間にわたるため、勉強時間の確保と継続が結果を左右します。
具体的な勉強法だけでなく、以下の3つを参考にしながら、どうすれば勉強を継続できるかを把握して日々の勉強に活かしていきましょう。
何をすれば合格できるのかを明確にする
志望校合格までに何をすれば良いのかを明確にし、勉強に迷わない環境を作ることが重要です。
具体的な目標を設定できると、何をどの順番で学習すれば良いかが明確になり、勉強への迷いが減るでしょう。
まず、志望校合格に必要な各教科の得点目標や、毎月・毎週の学習内容計画などの目標を決めます。
明確化する方法として、大学受験生の勉強をサポートする「鬼管理専門塾」では、1週間を5日と2日に分けて学習計画を組むのをおすすめしています。
5日間は勉強に集中する期間として、計画に沿って新しい内容を学習。
2日間は5日間の学習を復習する期間とし、学習した内容を定着させて理解を深める形です。

勉強に迷わないために具体的な学習計画を立てるのは重要ですが、1人で計画を立てるのは難しい場合もあります。
その場合はぜひ鬼管理専門塾にご相談ください。
努力の成果を記録する
毎日の勉強内容を記録することで、学習の進捗を確認し、自分の努力を実感できます。
努力したという達成感を得られれば、勉強のモチベーションを維持しやすくなります。
また、どの科目にどれだけ時間を割いたか、どの単元が苦手かなど、学習の傾向を分析するときにも役立つため、必ず記録しましょう。
自分ひとりで勉強の成果を管理するのが難しいと感じる方は、個別指導などを利用して講師からサポートを受ける選択肢も視野に入れてみてください。
模試の結果に一喜一憂せずに苦手克服に努める
勉強を継続するには、模試の結果に一喜一憂するのではなく、結果を活用して次のステップに進むのが重要です。
模試の結果が良かった場合、悪かった場合も、冷静に結果を分析しましょう。
特定の科目や問題形式がわからない場合、苦手部分を重点的に復習し、対策を立てる必要があります。
また、模試の結果に落ち込んでしまうなど、メンタルの浮き沈みがある場合は「リフレーミング」の活用がおすすめです。
リフレーミングとは、物事の見方を変えることで、ネガティブな状況をポジティブに捉え直す思考方法です。
たとえば、模試の結果が悪かった場合「自分にはまだ改善の余地がある」など、ポジティブな見方に変えられると学習へのモチベーションを維持できます。
リフレーミングを活用するのが難しいときは、ぜひプロの講師を頼ってみてください。

客観的な意見がもらえると、自分ひとりだけでは気づかなかった良い面を知れるチャンスが生まれるはずです。
実際に鬼管理専門塾では、講師によるリフレーミングをきっかけに、偏差値が上がって志望校に合格した生徒がいます。
高1~高3まで学年別の大学受験勉強の進め方
志望校合格に必要な勉強の進め方は、受験までの期間によって異なります。
ここでは、学年別の大学受験勉強の進め方を解説します。
自身の段階に合わせて、受験勉強を始める際の参考にしてみてください。
高校1年生|学習スタイルを定着させる
高校1年生の段階では、大学受験に向けた基礎を築くために、自身に合った学習スタイルを定着させるのが重要です。
高校の授業は中学よりも進度が速く、内容も難しくなるため、適切な学習スタイルを身につけることで「授業についていけない」状況を避けられるでしょう。
高校1年生の学習スタイルの基本は「予習」「授業」「復習」のサイクルを確立することです。
このサイクルを徹底することで、授業内容の理解が深まり、効率的に学習内容を定着させられます。
高校1年生の段階から、長期的な視野を持ち計画的に学習を進めることで、学年が上がった際、スムーズに受験勉強に移行できるでしょう。
高校2年生|志望校を決めて自分の学力差を把握する
高校2年生の段階では、志望校を具体的に決めて、現時点での学力差を把握しましょう。
志望校との差を明確にすることで、志望校合格に向けた効果的な学習計画を立てられます。
現状の差を埋めるためには、できるだけ具体的な計画を作成し、効率良く勉強を進めるのがポイントです。
具体的な学習計画の立て方は「大学受験の勉強を始めるときの準備」を参考にしてください。
高校3年生|基礎を固め実践的な勉強を進める
高校3年生では、まず基礎をしっかり固め、その後実践的な問題や過去問に取り組みましょう。
特に、夏までは基礎を固めることに集中しましょう。
基礎力がなければ、実践的な問題に取り組む際に理解が追いつかず、効果的な学習ができません。
基礎を固めた後は、実践的な問題や過去問に取り組むことで、応用力をつけていきましょう。
実践的な勉強を進める中でも、得意分野をさらに伸ばし、苦手分野を克服する意識が重要です。
高校1〜2年生の段階で基礎を固めていれば、高校3年生では実践的な学習に時間を割けます。
計画的に学習を進め、志望校合格に向けた実力を確実に身につけるのが重要です。
まとめ|自分に合った大学受験の勉強法で成績アップを目指そう
大学受験の勉強法は、自分に合った学習スタイルの確立や具体的な学習計画を立てるのが重要です。
志望校に合格するには、計画性をもって継続的に勉強を進めていきましょう。
しかし、一人ではなかなかモチベーションを保つのが難しく、挫折してしまうかもしれません。
そんな人には、大学受験合格をサポートしてくれる「鬼管理専門塾」がおすすめです。
鬼管理専門塾では、徹底的な鬼管理と充実した個別サポートで最短距離での志望校合格を目指せます。
「受験勉強で何をすればいいかわからない」「つい勉強をサボってしまう」という方は、ぜひ一度公式LINEから無料学習相談を受けてみてください。
あなたの受験の悩みや不安を解消します!
鬼管理専門塾のサポート方法が気になる方は、ぜひ下記の動画を参考にしてみてください。
大学受験の勉強法に関するよくある質問
大学受験の勉強法に関するよくある質問をまとめました。
今すぐに始めるのをおすすめします。
なぜなら、今が一番受験まで時間がある状態だからです。
一例として難関大学の受験には、約3,000〜4,000時間の勉強が必要と言われています。
1年間で志望校合格を目指す場合、1日あたりに換算すると平均8.2時間の勉強が必要です。
平日は6時間以上、休日は13時間以上と多くの時間が必要になるため、受験勉強を始めるのは早ければ早いほど良いと言えます。
下記の条件に当てはまる場合は独学でも問題ありません。
- 自分で勉強のカリキュラムを作成できる
- 勉強時間を自分で作れる
- 間違えている部分をすべて自分で分析できる
- どんなにつらい状況になっても自分でモチベーションアップができる
上記に当てはまる受験生であれば、独学でも志望校合格を目指せるでしょう。
しかし、そうではない受験生は、大学受験合格をサポートしてくれる「鬼管理専門塾」のような頼りになる講師からサポートを受けるのをおすすめします。
独学とは違い、知見を持った講師に助言をしてもらえると、受験勉強にかかる時間をショートカットできます。