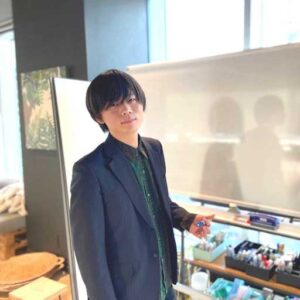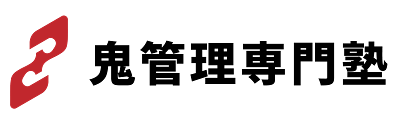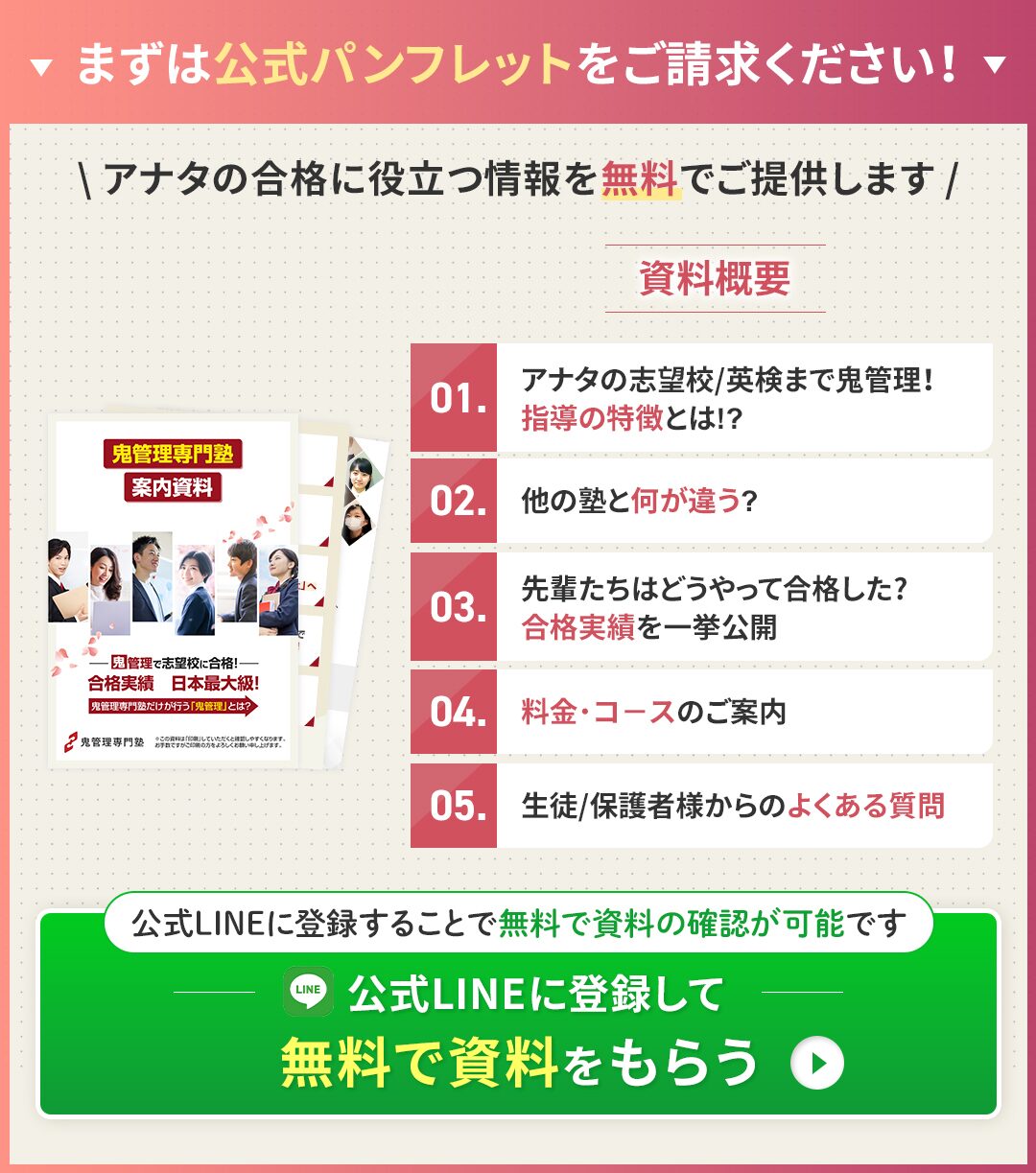始めに:偏差値30ってどれくらい? 偏差値30から合格しうるのか?
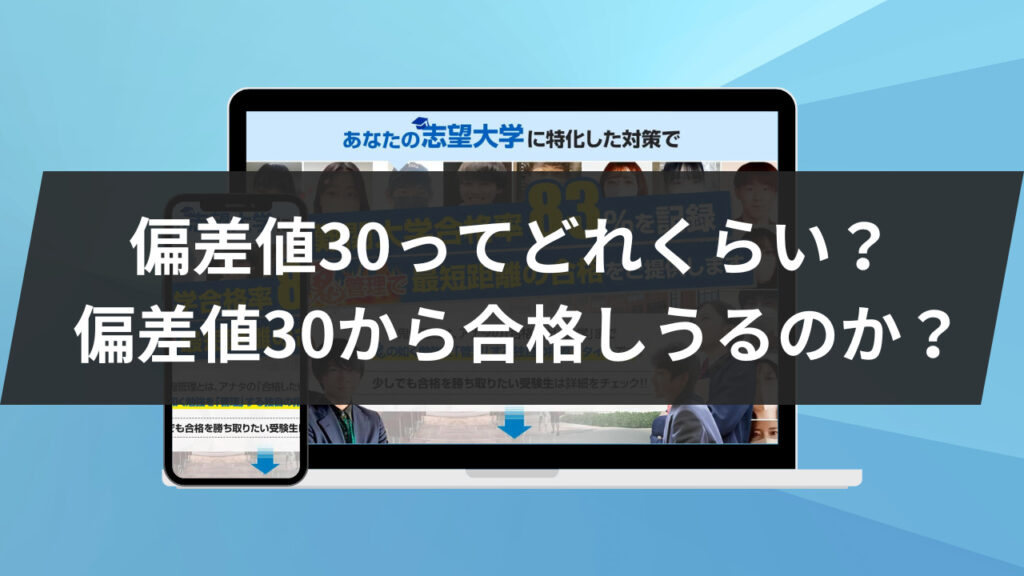

鬼管理専門塾を運営しております
代表の菅澤です!

鬼管理専門塾アシスタントのオニ坊です!
本日はどのような記事になりますか?

本日は
「偏差値30ってどれくらい? 偏差値30から合格しうるのか?」
というテーマで記事を書いていきます。
偏差値は、学習の進捗を知るための一つの目安として活用されています。多くの受験生は、この数字に一喜一憂しており、それをモチベーションにして学習を進めることも少なくありません。しかし、逆に偏差値が低いと、自分の能力に対する信頼や興味関心が失われることも。特に、偏差値30あたりの学生は、このような感情を強く持ちがちです。
偏差値30というと、一般的には平均よりもかなり低い数値と捉えられます。この状態から難関大学に進むことは果たして可能なのでしょうか?それとも、この数字はそのままの能力を示しているのでしょうか?
今回は、偏差値30というスタートラインからどれだけの努力と工夫で成果を上げることができるのか、そして偏差値30という数字が持つ実際のポテンシャルに迫ります。
偏差値30って?
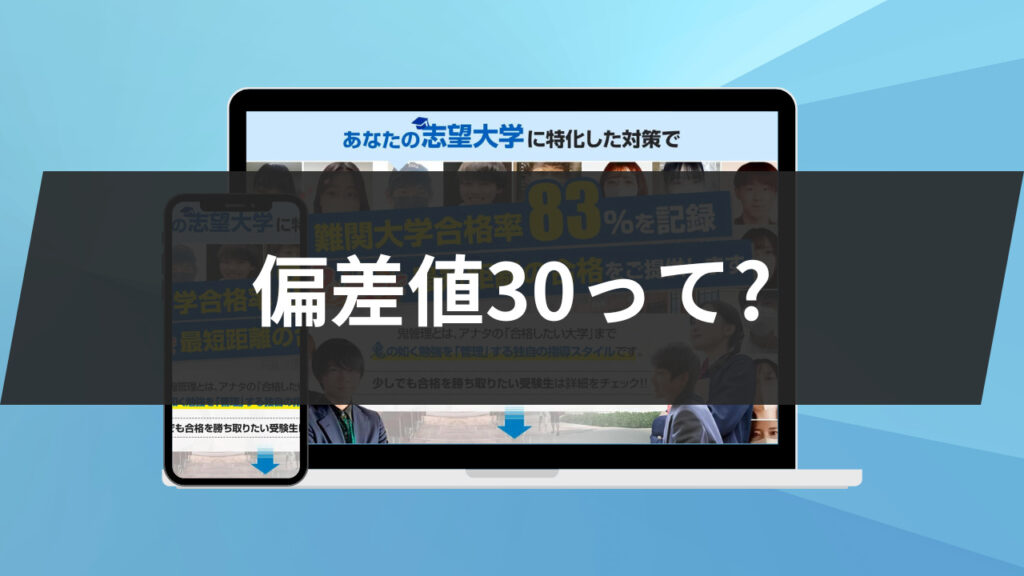

先ず、偏差値30って何を示しているのでしょうか?偏差値30は、試験やテストの結果から算出される数値のことを指します。偏差値について詳しくは後述しますが、大事なのは「偏差値は試験ごとに変わる」ということです。つまり、一つのテストでの結果が偏差値30であっても、別のテストでは偏差値が異なることが考えられるのです。

今回話している「偏差値30」とは、単に一度のテスト結果を示すわけではありません。複数のテストを受験し、その結果の平均が偏差値30となった場合を指しています。だから、その数値が学習の進捗や能力を示す一つの指標として参考にされるのです。

偏差値の基準点は50です。この値が示すのは、その点で全体の中央、つまり50%の位置にいるということ。これを具体的な人数にすると、100人中だとちょうど50人がその位置にいます。では、もし偏差値が30の場合、それはどれくらいの位置になるのでしょう?

実際に数値を見てみると、偏差値30は上位97.72%に位置するとされます。これを100人中で考えると、97人または98人の位置に相当します。一方、偏差値40の場合、それは上位84.13%、すなわち84人の位置となります。この違いから、偏差値が10点変動するだけでも順位に大きな差が出ることが理解できます。

偏差値30って、100点中だとどのくらいの得点なの?これは、まず偏差値の範囲を考慮しないと分かりません。例として、偏差値の上限が75、下限が25と仮定しましょう。このとき、偏差値の幅は50です。

その幅を元に、100点を等分すると、1偏差値が2点の価値を持つことになります。この計算で進めると、偏差値75が最高得点の100点、対照的に偏差値30は、100点中で実際には10点しか得られていないことになります。つまり、中央の偏差値50まで行くには、さらに40点が必要。偏差値30の位置は、実はかなりチャレンジングな位置にあるといえるでしょう。
そもそも偏差値って何?
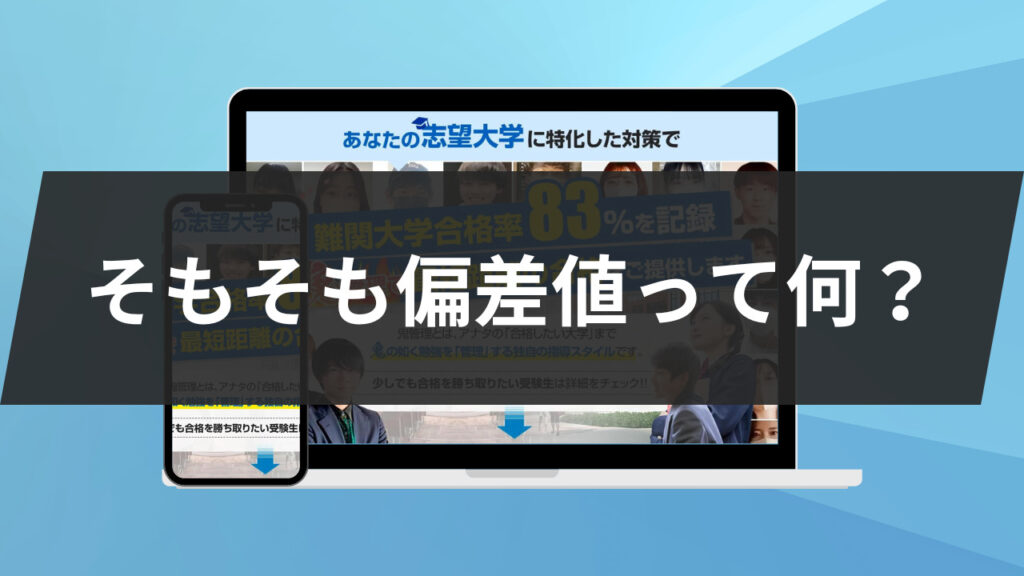

偏差値っていうのは、自分がどの辺に位置しているかを示す目安なんだよね。例えば、平均得点が30点でも、60点でも、自分の位置が同じなら偏差値も変わらない。だから、自分がどれくらいの位置にいるのかを一目で判断するための数値なんです。

偏差値30って言われると、その集団内での自分の位置がかなり低いということがわかる。つまり、中央の偏差値50に到達するためには、かなりの努力が求められるってこと。大学受験などでの評価は、相対的なものが多いから、この偏差値はとても大事な指標となります。つまり、自分がどれだけ頑張っても、他者との比較での位置が大事だということが、偏差値から学べるのです。

偏差値っていうと、基本的には0から100の範囲で考えられるよね。でも、実際には偏差値0や100っていうのはほとんど出てこない。実際、その確率って200万分の1だって言われてるから、超レアな存在。つまり、同じ年に生まれた人たち全員で試験を受けたとしても、偏差値0や100を取った人が1人も現れないことがあるんだ。

実際によく見かける偏差値は、偏差値20から80の間だね。これが全体の99.73%を占めるんだから、ほとんどの人がこの範囲に収まってるってこと。偏差値90や10の人は珍しいし、偏差値20や80の人たちが現れ始めるところ。だから、もし「最高の偏差値ってどれくらい?」って質問を受けたら、偏差値80くらいが上位の人たちのスコアだと思っていいよ。

これは簡単。偏差値っていうのは、真ん中が50なんだ。だから、平均的な得点っていうと偏差値50になるんだよ。これが、偏差値の基準点っていうか、中心になる数字なんだね。

偏差値って、受験の際のベンチマークになるんだよね。例えば、自分の得点だけ見ても「これって良いの?」って分かりづらいけど、偏差値なら「この点数だと、受験者全体の中でこんな位置にいるんだ」ということが一目瞭然。つまり、偏差値を知っていると、自分の実力を相対的に知ることができるわけ。

例えば、東大や京大を目指す場合、十分な偏差値がないと受験すらできないこともあるんだ。これを「足切り」とか言うんだけど、一次試験である程度の得点がないと、二次試験にすら進めないってシステム。だから、自分の偏差値を知っていると、それに見合った大学選びができるようになる。東大や京大だけじゃなく、他の大学も選択肢に入れられるんだ。

偏差値って、ただの数字だと思うかもしれないけど、それが高ければ高いほど自分の実力を実感できるよね。つまり、自分の偏差値を上げることで、自分の成果や努力が確認できる。それが、自分の自信に繋がるんだ。試験前に自分の偏差値を確認して「前よりも上がってる!」って実感できると、モチベーションも上がるし、自分の努力が形になって見えるから、さらに頑張ることができるようになるんだ。
偏差値30の受験生の共通点3つ
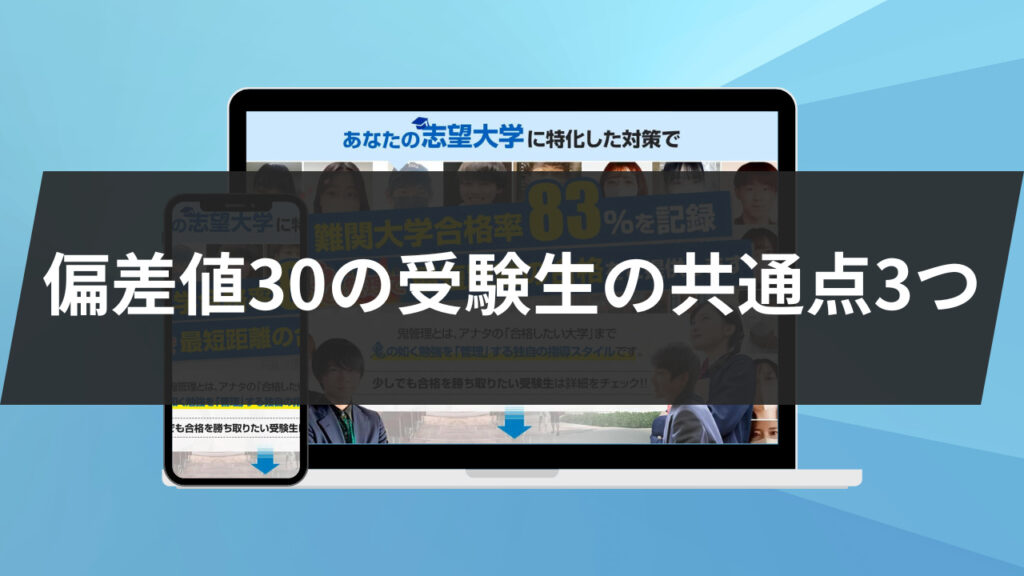
基礎がない
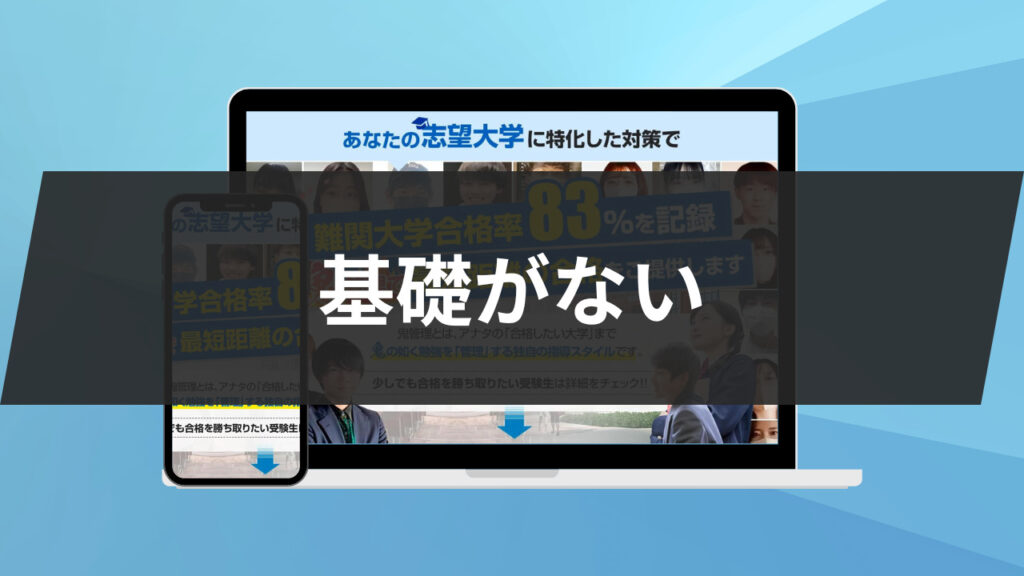
ゼロからのスタート
偏差値30って、ほんとに入門レベルだよね。これって、要は学問の土台や根っこがほぼないってこと。だから、そこには知識の空白が広がっているわけ。その空白を埋めるためには、本当に初歩からスタートしないといけない。
なんでそんなに基礎が必要なの?
知識って、建物を建てるときの土台のようなもの。土台がしっかりしていないと、どんどん高くなっていく知識の建物はすぐに崩れてしまうんだ。だから、基礎的な部分をしっかり理解しないと、上級の内容に進むことができない。偏差値30の人は、その土台部分が薄い。だから、まるで初めて文字を学ぶ子供のように、基礎からちゃんと学び直すことが必要。
基礎を築くのは大変?
正直、大変だよ。でも、それはどんな勉強も同じ。最初は難しくても、繰り返し練習することで、徐々に知識の土台がしっかりしてくる。偏差値30の状態からでも、ちゃんと努力すれば成果は出るんだ。でも、その努力の仕方も大切。ただ頭に詰め込むだけじゃなく、しっかりと理解するための方法を見つけることが大切。そして、それには時間や工夫も必要だけど、結果としての成長は確実に手に入るよ。
自分自身の実力を知らない
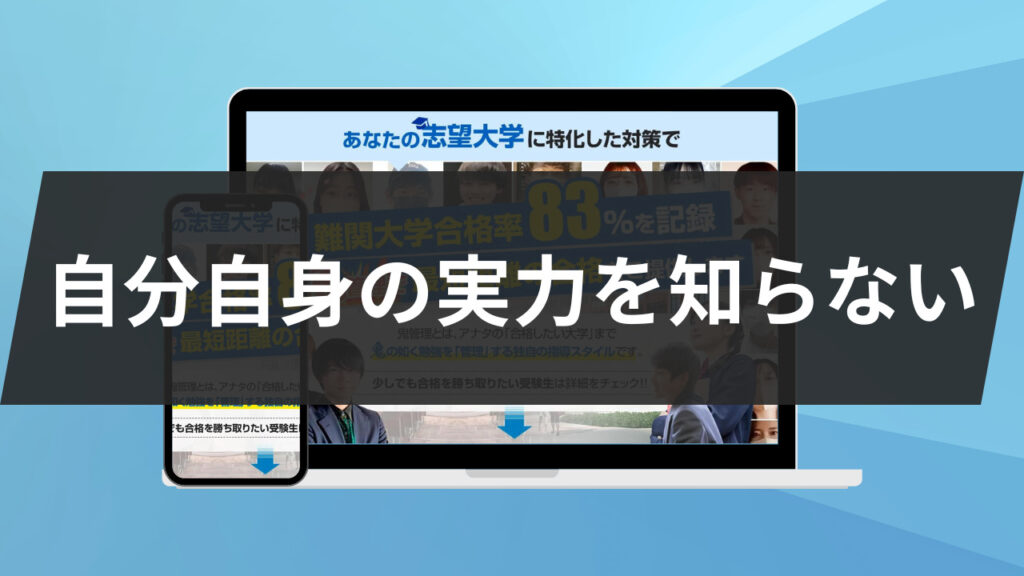
自分の弱点を知る
高い偏差値を持っている人って、自分がどんな問題でつまづくのか、また、それをどう解消すればいいのかが頭に入っているもの。だから、分からない部分が出てきたら、すぐに参考書やノートを開いて、その答えを探すことができるんだ。
知らないってことが、分からない
でもね、偏差値30くらいの人は、どこでつまづいてるのかさえ、意識できていないことが多いの。これは、基礎的な部分がまだしっかり身についてないから。だから、問題を見ても「どう攻めればいいの?」という第一歩さえ分からないんだよね。
一歩一歩、基本から
そんな状態の人たちは、まずは基礎からスタートし直す必要がある。それはまるで、赤ちゃんがはじめて歩くときのように、一歩一歩確実に進むこと。初歩の部分から丁寧に学ぶことで、今まで気づかなかった知識の部分や、理解のポイントに目が向けられるようになるんだ。そして、そこからさらに上を目指すためのステップが見えてくる。
勉強の仕方を知らない
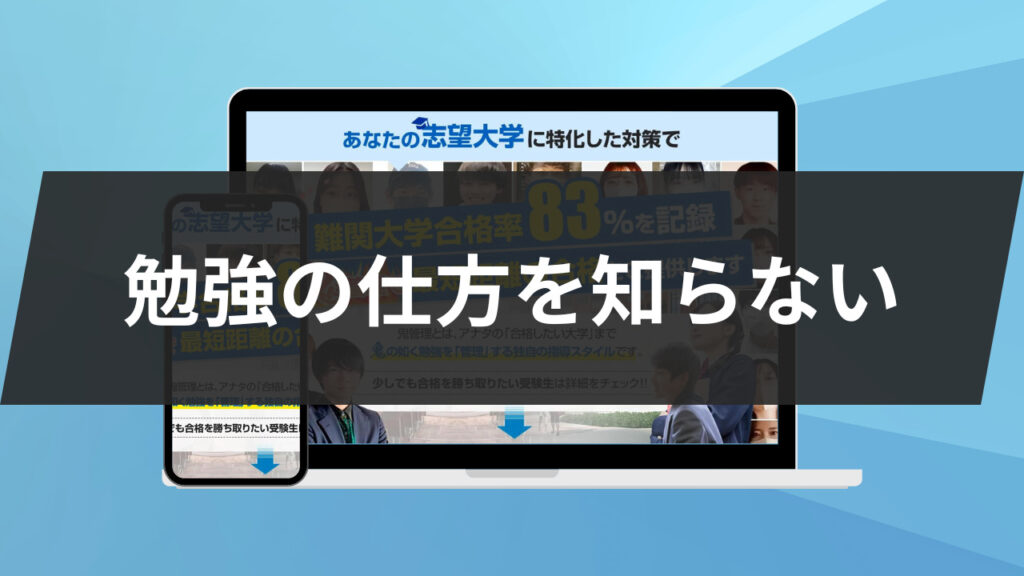
勉強のスタート地点を知る
偏差値って、実はちょっとした努力だけで大きく動くもの。特に、偏差値30という地点では、少しの努力で、すぐに35や40へと向上することが可能なんだ。でも、問題は「どうやってその点数を取るのか」という部分。
どこから手をつければいい?
「勉強する」って言っても、その方法や進め方がハッキリと分からないと、なかなか始めるのが難しいよね。さらに、勉強する習慣がないと、ただ机に向かうだけでもハードルが高く感じるもの。学校での授業内容を家で復習するという、学生としての基本的な行動さえ、意識的に取り組む必要があるんだ。
全ては基本から
偏差値30の状態では、何から手をつけていいのか、全くの白紙の状態かもしれない。だけど、それは逆に言えば、どこから始めても良いということ。最初は基本的なことからコツコツと積み上げることで、徐々に勉強への道筋が見えてくるはずだよ。
偏差値30から難関大学に合格するためには?
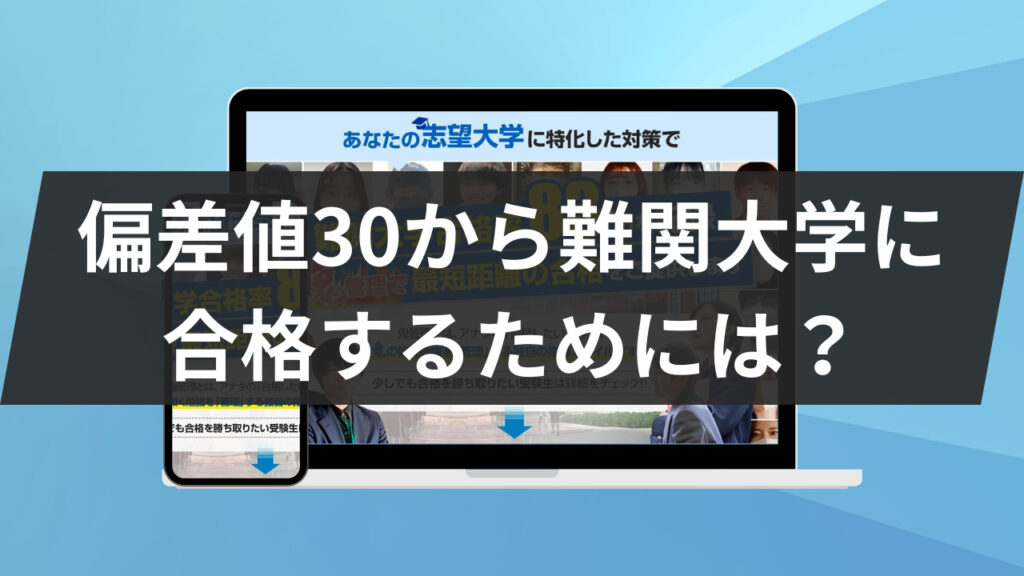

偏差値30のスタートラインからでも、トップクラスの大学に合格することは夢じゃない。もちろん、そこから早稲田や慶應、上智のような大学を目指すのは、決して簡単なことではありませんが、無理ではないんだよ。

では、どうしたらその大学の門をくぐることができるのか。まずは、勉強の習慣を身につけること。多くの受験生が日常的に行っていることが、偏差値30の地点ではまだ取り組んでいないことも多いのが現実。だから、最初の一歩として、毎日の勉強時間を増やすことが大切。

そして、もう一つ大切なのは「時間」。難関大学を目指すなら、一度の受験で合格するのは厳しいかもしれない。だけど、その結果を恐れず、浪人という選択肢を取り入れることで、さらに高い目標に挑戦するチャンスを手に入れることができる。辛い時間もあるかもしれないけど、その先に待つ成功の喜びは、その努力の価値があることを証明してくれるはずだよ。
偏差値30から難関大学に合格するための勉強法のコツ
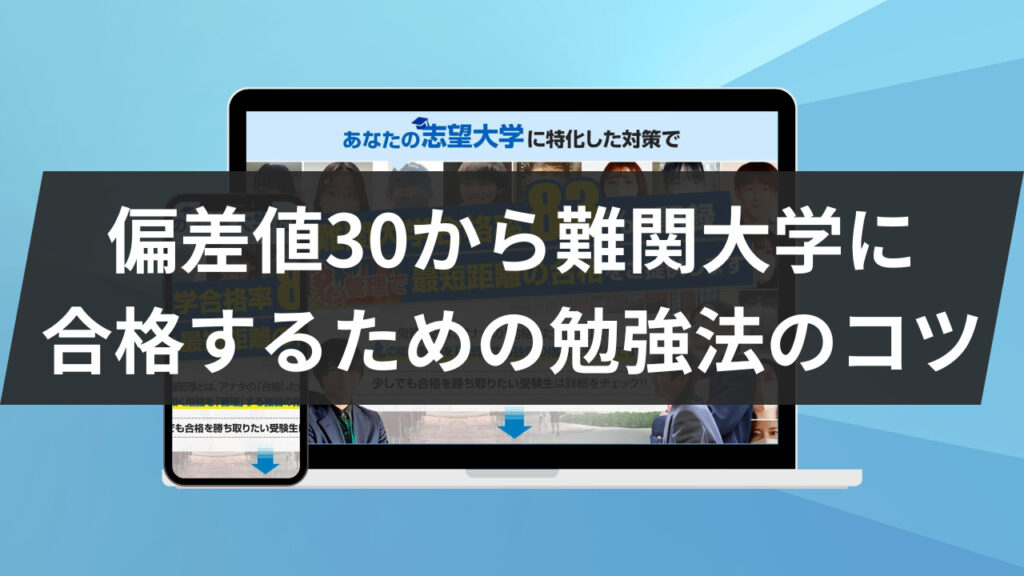
国語
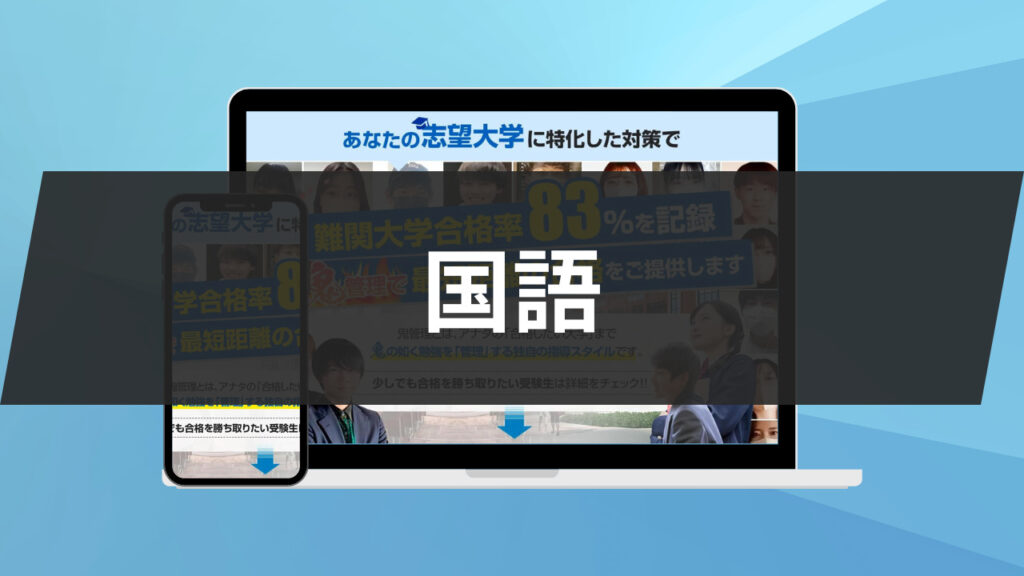
みんなの苦手、国語攻略法!
国語の学習は、いきなり難解な部分に飛び込むのではなく、基本から始めることが鍵となります。
語彙力をアップ!
まず最初に取り組むのは、語彙の向上。言葉の意味やニュアンスを理解することは、文章を読む力をグンと上げる手助けとなります。具体的には、漢字の検定試験をうまく利用しましょう。5級からスタートして、じわじわとレベルアップしていくのがおすすめ。いきなり高いレベルの漢字を目指すより、段階的に挑戦することで自信を持ちつつ、確実にスキルアップできます。
現代文の攻略
次に、現代文の問題解決のテクニックを掴むためのステップ。最初は初心者向けの参考書を使って、基本的な解き方やポイントを習得。この段階で、文章の構造や主旨を掴む練習をしっかりと行いましょう。
着実なステップアップ
国語の学習は、劇的な進歩を期待するより、日々の積み重ねが大切。基本をしっかり身につければ、その後の進展は驚くほどスムーズに。コツコツと基礎からの取り組みで、目指す偏差値への道を切り拓きましょう!
数学
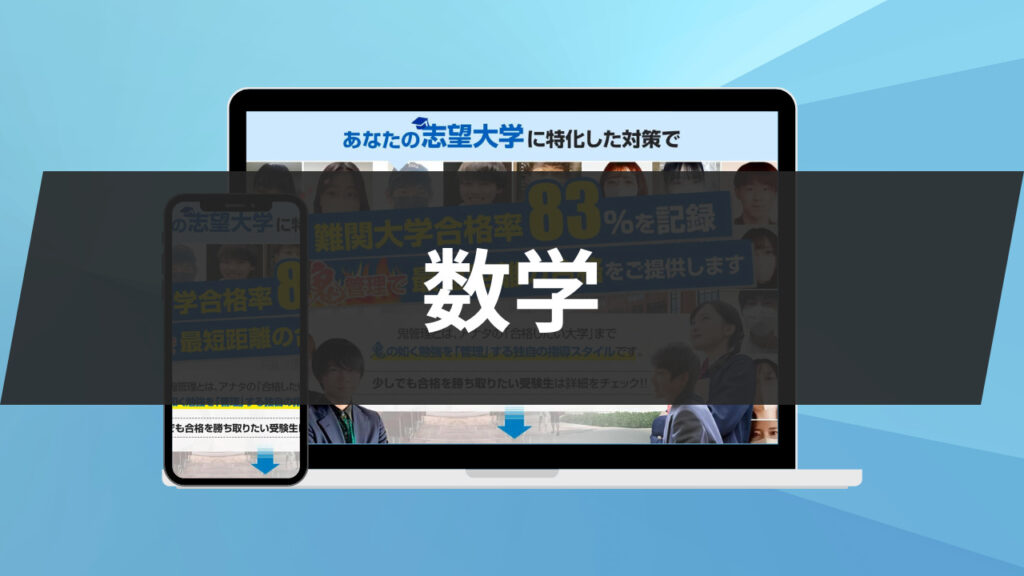
数学マスターへの初歩!
数学は一歩一歩、確実に進めることで理解が深まります。だから、高い目標を持つ前に、しっかりと基本を固めることが大切です。
スタートは中学数学から
数学の学び直しは、中学の内容から取り組むのがベストです。なぜなら、高校数学の多くのトピックは、中学で習得した知識を前提として進行するため。中学の内容に自信がないと、高校数学の問題に挑戦するのは難しいでしょう。
基礎固めのためのチャート活用
中学の内容を理解したら、次のステップとして「白チャート」を使って高校数学の基礎を固めていきます。このチャート式の教材は、初級から順に学べるように設計されているので、自分のペースで進められます。白チャートをマスターしたら、次は黄色のチャートを手に取り、さらに難易度を上げていきます。そして、そのレベルをしっかりと身につければ、偏差値60を目指すことができるようになるでしょう。
最終ステップ:過去問に挑戦!
基礎がしっかりと身についたら、大学入試の過去問題を使って演習を重ねることが大切です。この段階で多くの問題を解くことで、実力を確実に上げることができます。
英語
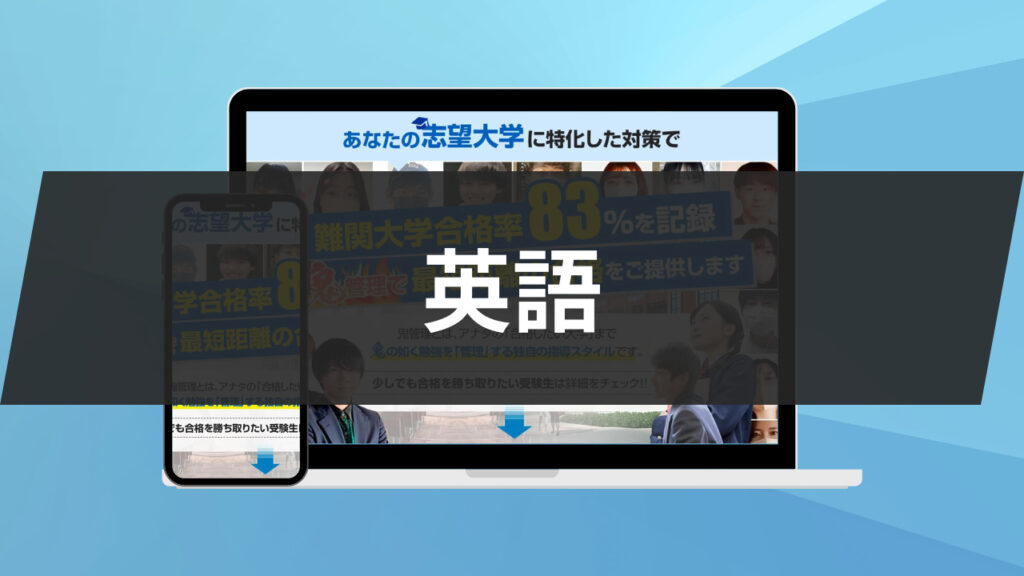
英語攻略の第一歩!
英語はコミュニケーションのツールとしてだけでなく、受験のためにも必要なスキルです。英語力を伸ばすための効果的な方法を紹介します。
語彙・文法をしっかり!
英語の基礎となるのは、やはり語彙と文法です。これらをしっかり学ぶことで、英文の理解が格段にアップします。特に、英検を利用すると、自分の現在のスキルを確認しながら、段階的にスキルアップを目指せます。
英検で目標を設定
英検5級をスタートラインとして、語彙や文法の基礎を固めていくことが大切です。そして、英検の各レベルを通過することで、自分の英語力の成果を実感できるでしょう。特に英検準1級に到達することができれば、難関大学の英語試験にも自信を持って臨むことができます。
基礎からのステップアップ
英語学習は長い道のりと感じるかもしれません。特に、偏差値30のスタート地点からは、平均的な学生よりも一歩一歩の努力が必要となります。しかし、一つの段階をクリアするごとに、自分の成長を実感できるのも英語学習の魅力です。文法や語彙を地道に増やしていくことで、自然と読解力やリスニング力も向上します。
理科系
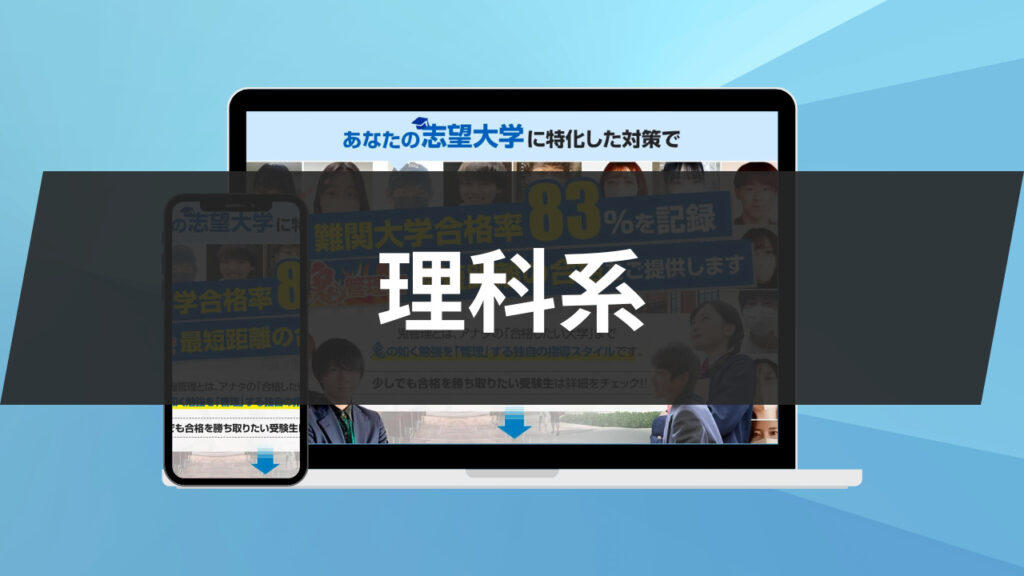
理科攻略のヒント!
理科は実験や観察をもとに構築された知識の集積です。この分野にはいくつかの科目がありますが、ここでは特に「生物」に焦点を当てて、その学習方法を考察します。
生物は暗記力を鍛えるチャンス
「生物」は他の科目と比べて、暗記が必要な部分が多いです。しかし、それは逆に言えば、しっかりとした暗記方法を身につけることで、得点をしっかりと固めることができる科目とも言えます。生物の用語や概念を一つひとつ確実に頭に入れることが大切です。
基礎からのアプローチ
生物の学習をスタートする際は、まず基礎的な内容から手を付けることをおすすめします。たとえば「生物基礎」という教科書や参考書が役立ちます。基礎からしっかりと理解を深めていくことで、より高度なトピックにもアプローチしやすくなります。
視覚を利用した学習法
生物には様々な生き物や構造が登場します。これらを単なる文字情報としてだけではなく、図やイラストを利用して視覚的に捉えることで、記憶の定着を助けることができます。特に生物の構造や生命現象を理解する際には、イラストや模式図を見ながら学習することで、より深く内容を理解することができるでしょう。
社会科系
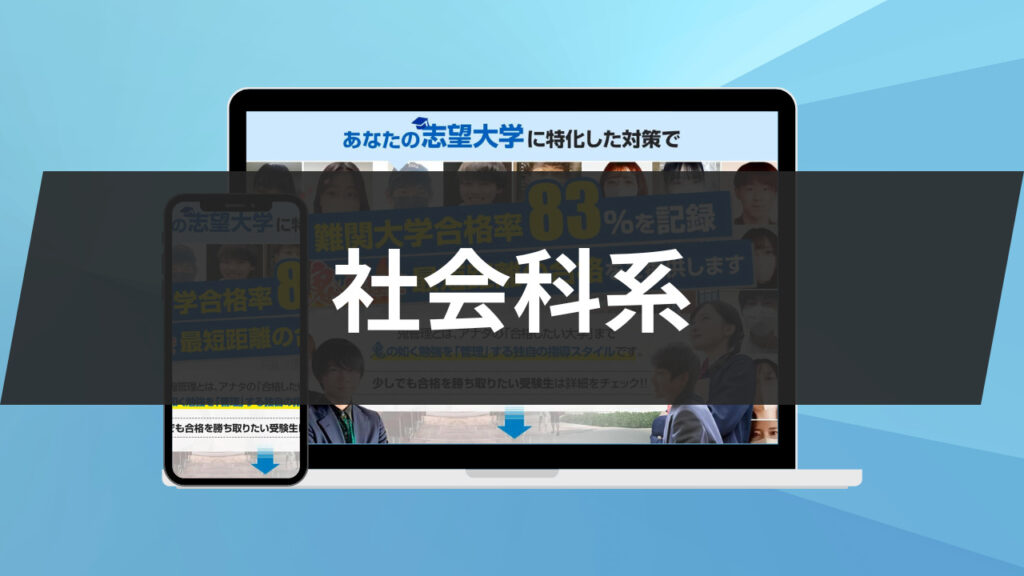
社会の楽しい学び方!
社会の教科は歴史や政治、経済など、私たちの日常や文化の背景を学ぶ素晴らしい分野です。それゆえ、こうした科目はただの暗記だけでなく、楽しみながら学ぶことが大切です。
歴史を物語として楽しむ
社会の中でも特に「歴史」は、過去の出来事や人物を通して、様々なストーリーやドラマを知ることができます。初めは、ストーリー性のある参考書や漫画などを選び、歴史の面白さを感じ取りましょう。物語のように展開する歴史のエピソードに興味を持てれば、勉強そのものが楽しみになります。
全体像の把握
歴史や社会の出来事は、それぞれが繋がっています。そのため、講義形式の参考書や動画などを用いて、時代背景や全体の流れを掴むことが大切です。そうすることで、個々の事象や人物もより深く理解することができるようになります。
重要なポイントの確認
社会の勉強では、特に重要な語句や事象を覚えることが求められます。これらの要点をノートにまとめたり、フラッシュカードを使用して暗記するなどの方法が効果的です。
アウトプットを大切に
理解した内容をしっかりと自分のものにするためには、アウトプットが欠かせません。過去の問題集を利用して問題を解いたり、自分なりにまとめたりすることで、知識を定着させましょう。
社会は日常の中で繰り広げられるストーリーの宝庫。興味を持ち、楽しみながら取り組むことで、学習の効果も大きく上がりますよ!
偏差値30から難関大学に合格する1年間の勉強法
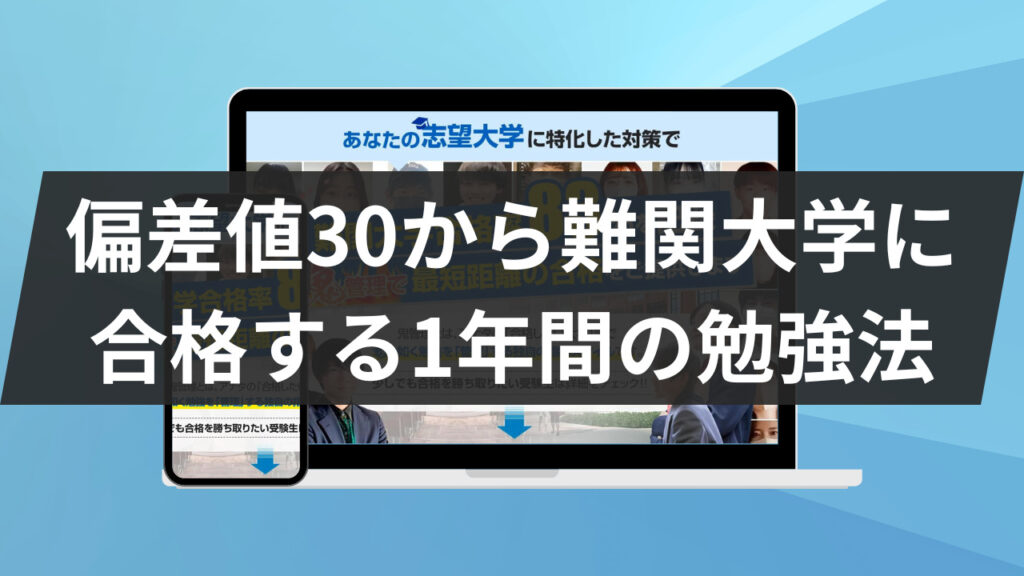
4月から6月
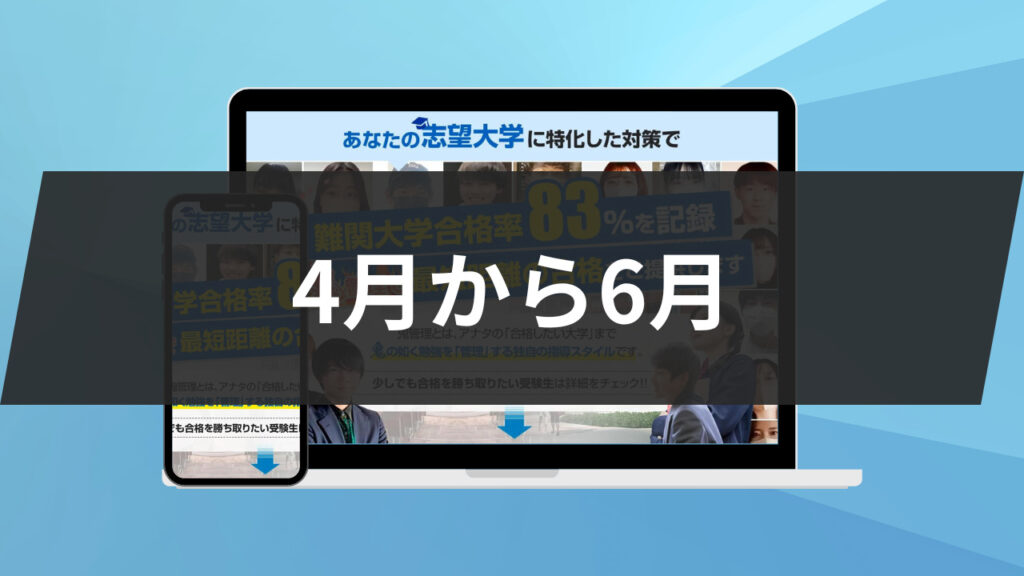
4月から6月は、新しい学年のスタートとともに学びの基盤を築く大事な時期です。この期間をうまく使って、後の学習に強い土台を作っていきましょう。
みんなの基礎チェック
新しい学年の始まりには、それぞれの教科で必要な基本的な知識や技能の確認を行います。これは、新しい学びのための土台づくりとして非常に重要です。
教科ごとの基礎強化
- 国語: 漢字の読み書きや日常で使う語句の確認を行いましょう。これにより、読解問題や作文の際にスムーズに文章を読み解くことができます。
- 数学: 公式や基本的な計算方法をしっかりと頭に入れます。これらは、複雑な問題を解く際の道具のようなものなので、しっかりと身につけておくことが大切です。
- 英語: 基本的な単語や熟語、そして文法ルールを確認していきます。これにより、英文の読解や英作文がしやすくなります。
基礎は体力づくり
学問の基礎を身につけることは、スポーツでいうところの体力づくりや基本動作の練習に似ています。しっかりとした基盤があれば、後の学びがよりスムーズに進みます。
早めの完了を目指して
理想的には、夏までに基礎を固めることが望ましいですが、できるだけ6月までに終わらせてしまうことで、夏休み以降はより高度な学習や演習問題に集中することができます。早めのスタートで、後の学びを有利に進めていきましょう!
7月から9月
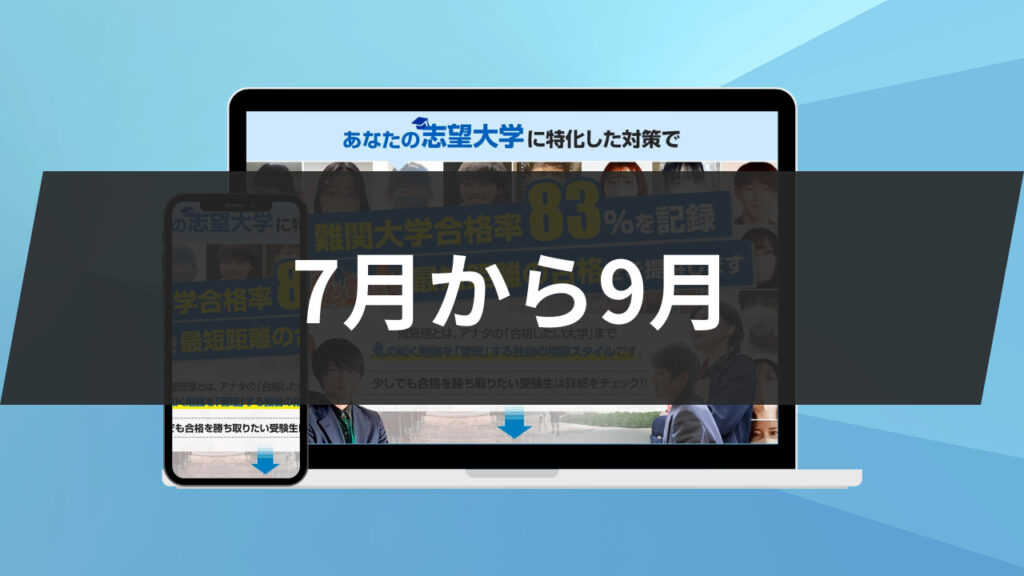
夏休みの期間は学びの黄金期ともいえる時期です。この時期を有効活用して、学習の質と量をしっかりと確保することが重要です。
夏の2ステップ勉強法
夏休みの時期は、基礎知識の復習とともに、高度な演習問題にも取り組む良いチャンスです。この2つのアプローチをバランスよく進めることで、学力の向上を実感できるでしょう。
演習問題の正しい取り組み方
演習問題に挑む際、最初から全ての問題を解くことを目指すのではなく、まずは問題の解説やヒントを確認しましょう。これにより、問題のポイントや解き方のコツを掴むことができます。
確認&再確認
解説を元にして問題に再挑戦することで、自分の理解度をチェックできます。そして、解説を見ずに正確に問題を解けるようになるまで、同じ問題を何度も解くことをおすすめします。
頭の中の図書館を作ろう!
参考書やテキストの内容を完璧に頭に叩き込むことで、テストや試験の際に迷わず答えを導き出すことができるようになります。この時期にしっかりと頭の中の知識のストックを増やし、試験に備えることで、合格への道が開けてきますよ。
10月から12月
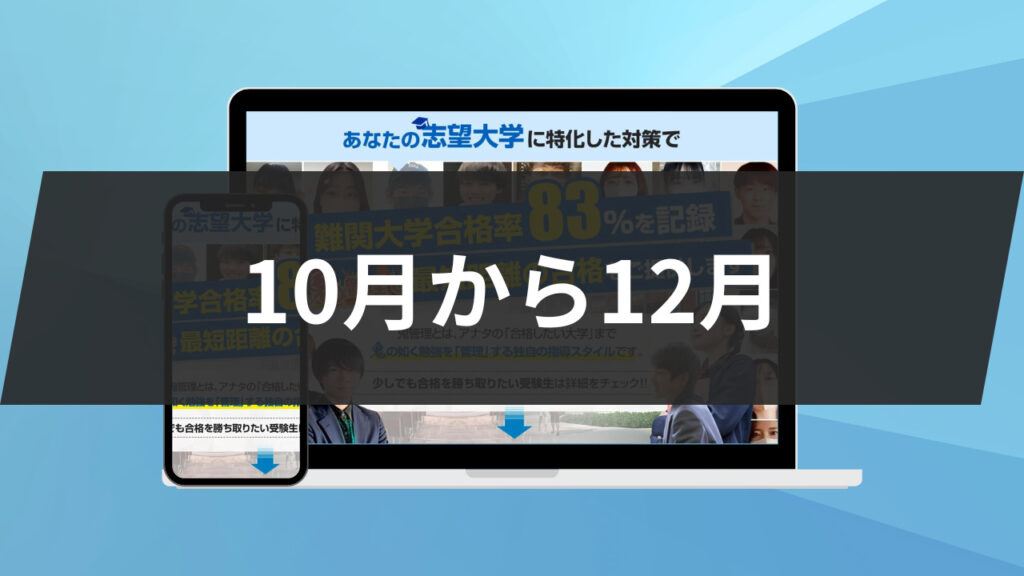
年度も後半に差し掛かり、これまでの勉強の成果をしっかりと結実させるタイミングが到来します。秋のこの時期は、試験に向けた総仕上げの期間となるため、どう取り組むかが合否を分ける重要な局面と言えます。
演習の大量攻勢!
基礎知識を固めた後のこの時期は、多くの演習問題に挑戦して実力を養成する段階です。特に過去の試験問題は、今後の試験の出題傾向を知る上で欠かせないツールです。
模試の反復練習
模擬試験は、実際の試験にどれだけ近い状態で問題を解くことができるかをチェックする大事なツールです。間違えた部分や不得意なポイントを洗い出し、それを基に更なる学習計画を立てることができます。
最終チェックの時間
秋の終わりには、入試直前の最終確認の時間を設けることが大切です。ここでの取り組み方次第で、本番の試験にどれだけ自信をもって挑めるかが変わってきます。
積極的なアクション
分からない問題や弱点が明確になった場合は、それを放置せずに積極的に取り組むことが重要です。この時期は、まだ修正や改善が可能な最後のチャンスですので、全力で挑む姿勢が求められます。
1月から受験日まで
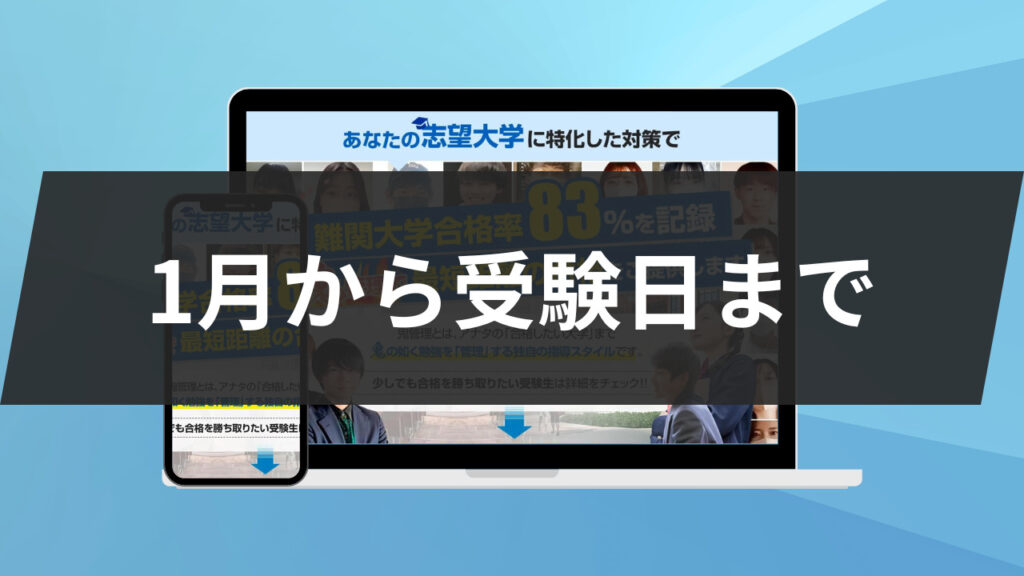
受験までの残された時間は、あとわずか。この短期間にどれだけ効率よく、確実に力をつけられるかが鍵となります。そのための取り組み方や心がけを以下に紹介します。
1冊の完璧主義
この時期は、参考書や教材を広く浅く取り組むよりも、1冊を深く徹底的にマスターすることがオススメです。1冊を隅々まで理解し、自分のものにすれば、それはまるで頭の中に知識の宝庫を持っているようなもの。それが、試験当日の自信となり、確実な点数へとつながるでしょう。
万全の状態を目指して
最終直前の勉強は、確かに追い込みの大事な時期ですが、過度なプレッシャーや過労は避けたい。無理をせず、健康を第一に考えつつ、効率的な学習を心がけることが大切です。必要以上に焦らず、自分のペースで確実に力をつけていくことを意識しましょう。
秋の取り組みの重要性
もちろん、この時期の勉強も非常に大切ですが、それを余裕をもって進めるためには、前の時期、特に秋の勉強が大事です。十分な下準備と基礎固めがあるからこそ、受験直前の勉強もスムーズに進めることができるのです。
最後に:第一志望校に合格するには?
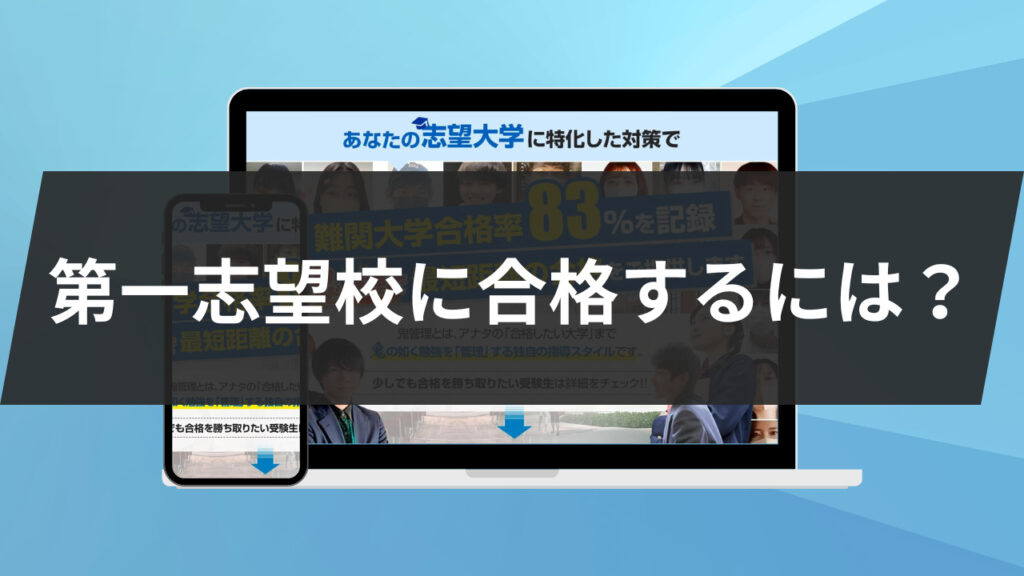

ここまで偏差値30から合格できるかについて見てきましたが…、

偏差値30というゼロの状態から合格するのは難しいことですが、不可能ではないことがわかりましたね。

本記事監修者 菅澤 孝平
シンゲキ株式会社 代表取締役社長
「鬼管理」をコンセプトとした「鬼管理専門塾」を運営。
大学受験・高校受験・英検指導・総合型選抜に幅広く展開しており、日本全国に受講生が存在している。
出演番組:カンニング竹山のイチバン研究所・ええじゃないかBiz
CM放送:テレビ東京など全国15局に放映